Machisaisei concept
まちを耕す人を
つくる
人が土壌を耕すと、土は呼吸し、植物は根をはり、
生物は健やかに活動します。
生活の土壌である「まち」もまた、
多様な人がいきいき暮らす場所にするには、
人が手を加え、新たな風を入れることが必要です。
まち再生コースは、
そんな「まちを耕す人」になるために、
都市計画・まちづくり・建築の再生・企画デザインといった
幅広い領域から課題を見つけ、考え、創る力をつける学び場です。
人・空間・社会の視点を持って、
自らまちを歩いて発見する。
興味をとことん掘った先には、
きっと新しい可能性が見つかるはずです。
ここで培った、あなただけの知の力で。
さぁ、まちを耕す人になろう。
laboratory
まち再生コースの研究室
都市計画研究室
「人々が豊かに暮らせる都市を考える」
社会や制度、文化、生活などを反映して、時代とともに都市は変容します。私たちは、その変容をさまざまな視点から調査・分析し、新しい都市のカタチを提案しています。現代の都市は、商業やビジネスを核として集積し、国際化やIT化の影響を大きく受けていますが、これからの少子高齢化を考えると、これまでの都市計画のように成長と拡大を前提とするのではなく、縮小していくことをイメージしていく必要があるのは明白です。同時に、変わりゆく都市を構成する建築の在り方も考えなければなりません。 当研究室では、このような問いに研究やプロジェクトを通して回答すべく、住民参加型ワークショップの運営などを通してまちづくりの現場にも積極的に関わっています。
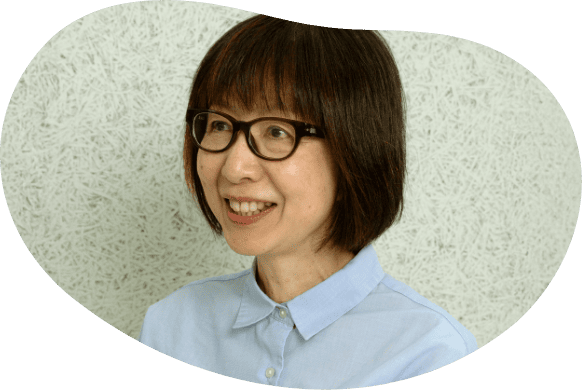
都市計画研究室
山家京子 教授

都市計画研究室
柏原沙織 助教
建築保存活用研究室
「"継承設計"の取り組みにより、価値を受け継ぐ建築やまちづくりを行う。」
従来ではスクラップ&ビルド(解体と新築)によって街の機能更新が行われてきましたが、これからの時代はストック(既存の建造物)をリノベーション(改修)やコンバージョン(用途転換)によって再生することが求められます。特に、歴史的建造物には、唯一無二(たったひとつ)の価値があります。 その価値を明らかにした上で継承しつつ、機能面ではこれからの時代に対応し生まれ変わらせることで、新築にはできない建築を生み出すことができます。そのような取り組みを「継承設計」と呼び、さまざまな価値継承の方法について研究しています。

建築保存活用研究室
野村和宣 教授
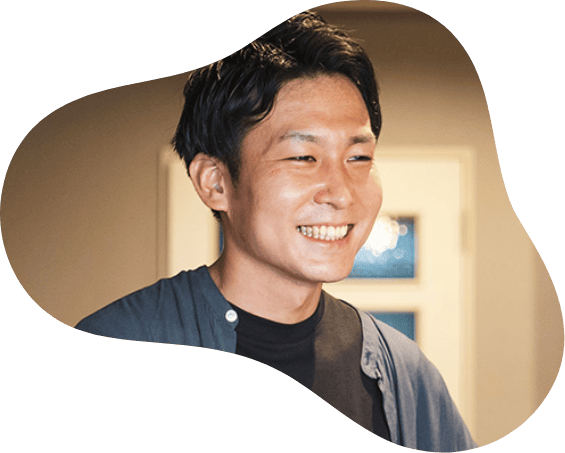
建築保存活用研究室
塩脇祥 助手
不動産デザイン研究室
「建築と不動産のあいだを追究し、社会課題をデザインで解決する。」
建築学と不動産学の架け橋となるこの研究室は、これまでの建築デザインやまちづくりの領域に、不動産やマーケティング・ファイナンスの知識を導入するという、日本でも新しい取り組みを行います。 世界各国と比較すると、日本はこれまで新しい建物を大量に作ってきました。それは同時に、大量に建物を壊してきたとも言えます。そして壊しきれない空き家が余っているという、無駄の多い状態であることは否めません。そうした建てれば良い時代は終わり、いかに持続可能な建築やまちの在り方を考えるためには、自然と不動産という分野に真摯に向き合う必要があるのです。
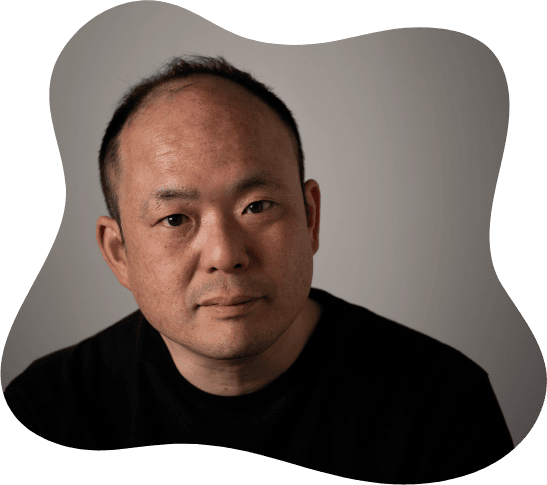
不動産デザイン研究室
高橋 寿太郎 大学実務家教授
まちづくり研究室
「人々が豊かに暮らせる都市を考える」
社会や制度、文化、生活などを反映して、時代とともに都市は変容します。私たちは、その変容をさまざまな視点から調査・分析し、新しい都市のカタチを提案しています。現代の都市は、商業やビジネスを核として集積し、国際化やIT化の影響を大きく受けていますが、これからの少子高齢化を考えると、これまでの都市計画のように成長と拡大を前提とするのではなく、縮小していくことをイメージしていく必要があるのは明白です。同時に、変わりゆく都市を構成する建築の在り方も考えなければなりません。 当研究室では、このような問いに研究やプロジェクトを通して回答すべく、住民参加型ワークショップの運営などを通してまちづくりの現場にも積極的に関わっています。
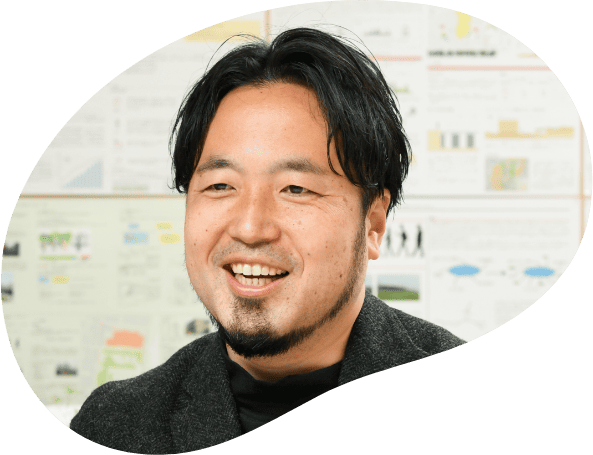
まちづくり研究室
上野正也 准教授
